「本、読んでますか?」
通信制 一ツ葉高校 小倉キャンパス 早尻です。
皆さん、こんにちは。今日は、私が思う、文章読解のポイントについてお話したいと思います。私たちが目にする文章は、主に説明的文章(評論文)と文学的文章(小説など)に分けることが出来ます。
説明的文章では、筆者の主張を要約することが大切ですが、これを筆者の立場から考えてみましょう。文章を書くということは、なにがしかのエネルギー(動機)が必要であり、あるテーマについて、自分はこう思うという主張があり、それを読者に賛同してもらいたくて文章を書きます。ですから読者に納得してもらうために、実例をあげたり、たとえ話をしたり、科学的実験データを添えたり、理屈、根拠を述べたり様々な工夫を凝らします。「なるほど、鋭い指摘だな。」「ユニークな考え方だな。」と支持してもらいたいわけです。筆者が読者から指摘されて、最も落ち込む批判は何だと思いますか。おそらく、「当たり前じゃん。だから何なの。」という類のコメントでしょう。ですから、筆者は、当たり前のことは書きません。もし、要約した結論が極めて当たり前の場合には、筆者が本当に主張したいのは、結論そのものではなくて、結論に至るプロセス(理由や根拠)であることがあります。例えば、「森林破壊は良くない。」という結論があったとします。このこと自体は、多くの人が認める(反論出来ない)事実ですが、筆者の本当の主張は、そのことが地球環境にどのような影響を及ぼすかという点にある場合などです。
説明的文章では、キーワード(文化、芸術、環境など)が繰り返し出てきますが、一般的意味以外に筆者がその言葉に新たに付加した意味が読み取れる場合には、そこが筆者独自の見解になっています。この独自の見解こそが筆者が最も主張したい点です。
次に文学的文章について考えてみましょう。文学的文章を鑑賞する場合には、登場人物の感情変化(喜怒哀楽)を追体験することが大切です。しかし、小説では、誰々が、・・・「喜んだ」「怒った」「悲しんだ」などの表現はほとんど出てきません。なぜなら、作者は「喜んだ」という言葉を使わずに喜びを表現し、「悲しんだ」という言葉を使わずに悲しみを表現しようとするからです。登場人物の行動描写と会話文の中に、間接的な感情表現が散りばめられています。そこを読み取ることが、文学的文章にふれる魅力のひとつではないかと思います。
通信制 一ツ葉高校 小倉キャンパス 早尻
 通信制高校
通信制高校
 通信制高校 一ツ葉高校
通信制高校 一ツ葉高校  キャンパス紹介
キャンパス紹介 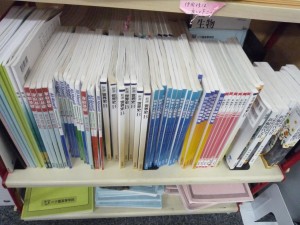










 0120-277-128
0120-277-128